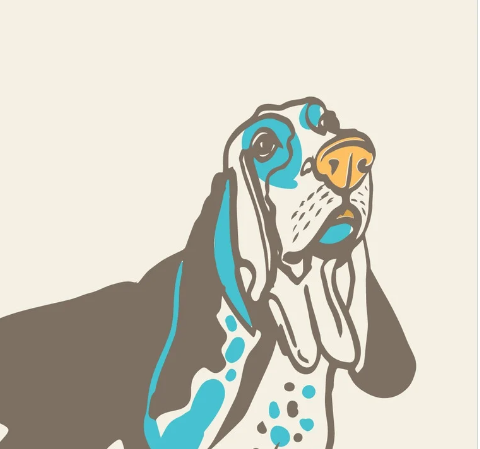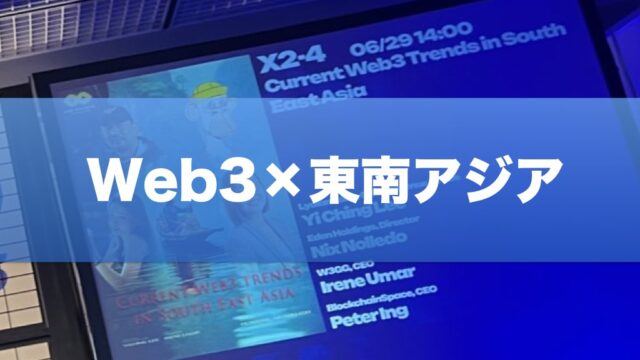2023年6月28日(水)~6月30日(金)に京都で行われた、IVS Crypto 2023 KYOTOに参加してきました。会場では、Web3や暗号資産に関連する様々な議論や催し物が開催されました。本記事では、【Web3×VC】に焦点を当てて、Web3領域の動向を考察してみたいと思います。
- What Do VCs Care About These Days Before Investing in Web3(Web3に投資する前に、VCは何を気にしているのか?)
- WiL, Partner – 久保田 雅也氏
- KX Venture Capital, Executive Director – Jom Vimolnoht氏
- HashKey Capital, Partner – Xiao Xiao氏
- CMT Digital, Investment Partner – Augustus Ilag氏
- OKX Ventures, Partner – Yunan(Jeff) Ren氏
- Web3 Games Investment thesis from VCs(ベンチャーキャピタルによるWeb3ゲームの投資テーマ)
- Animoca Brands, Advisor – Richard Robinson氏
- Big Brain Capital, General Partner – Sam Kim氏
- Binance Labs, Investment Associate – Nicola Wang氏
- Infinity Ventures Crypto, Venture Partner – Dan Wang氏
- Animoca Ventures, Head – James Ho氏
投資のバランス:インフラ vs アプリケーション
Web3系のVC投資は当初ブロックチェーン技術などのインフラ面への投資から始まりましたが、昨今ではゲームを初めとしたアプリケーション層への投資も増えてきています。それぞれどちらに注力した方がいいのか(どちらが業界を主導していくのか)という議論はしばしば取り上げられますが、まずその点について述べておきます。結論、インフラ面もアプリケーション面も両方バランスを持って投資をしていった方が良いと考えています。これらは、業界の発展には両者共に重要なポイントであり、両方が相互に補完しあって成長を促進するためです。
インフラ面への投資は、ブロックチェーン技術そのものの進化を支えます。Web3領域が持続的に成長するためには、信頼性の高いブロックチェーンプロトコルやスケーラビリティの向上が不可欠です。また、セキュリティやネットワークの安定性も重要な要素です。Web2の成功例を振り返ると、TCP-IPレイヤーやデータレイヤーの確立がインフラ面での進化をもたらし、それによってアプリケーション層の発展が可能となりました。
一方、アプリケーション層への投資は、具体的なユースケースやニーズに基づくプロダクトの開発を促進します。具体的なアプリケーションやWeb3ゲームの発展により、ユーザーからの需要がインフラ面に対して新たな要望を生み出すことがあります。この相互作用により、ユーザーのニーズを満たすために適切なインフラが整備され、エコシステム全体の成長が促進されます。
実際、2018年当時はレイヤー1やレイヤー2系(インフラ面)のプロジェクトが時価総額の大半(70%〜80%)を占めていましたが、現在は50%〜60%に減少し、アプリケーション層のプロジェクトの割合が増加してきています。持続的な成長を実現するためには、インフラとアプリケーション層のバランスを見極めながら、適切な戦略を取ろうという動きが広まりつつあるのです。
Web2からWeb3への転換と必要な要素
さて、Web2のベテラン勢がWeb3領域で活躍するためには何が必要となるのでしょうか。まず、彼らが持っている既存のゲームIPやゲームユーザー(ファン)を活かすことで、Web3でエコシステムを構築することが重要です。Web3におけるゲームは、ユーザーにとってリアルな所有権や収益の可能性を提供することができます。この特性を活かして、既存のゲームのファンをWeb3ゲームへと引き込むことが成功の鍵となります。実際に、AnimocaのようなWeb3領域で活躍する企業は、様々なパートナーと協力し、彼らの持つリソースやネットワークを活用してエコシステムの構築を進めています。
さらに、Web2企業からWeb3企業への転換では、マーケティング戦略の変化が必要です。代理店とのやり取りが主流であり、直接的なユーザーコミュニケーションが不要だったWeb2に対して、Web3では早い段階からコミュニティを形成し、ユーザーとの積極的な関わりを持つことが鍵となります。Web3におけるコミュニティは、単なるユーザーでなく、初期投資家としても機能し、共にプロジェクトを支えていくパートナーとして重要な役割を果たすためです。これはWeb2との大きな違いでもあります。
気をつけるべきもう一つのポイントは、常に変化する環境に適応する姿勢をもつことです。Web3はまだ若い領域であり、確固たる基盤が定まっていません。そのため、ユーザー目線・顧客目線を重視し、彼らが求めるものを理解して柔軟にアプローチしていく必要があります。Web3におけるゲームとは何かを常に考えながら実験を繰り返し、失敗を恐れずに前進する姿勢と、Foundation of Conviction(確信を持った基盤)を持つことが求められています。
Web3ゲームの未来展望
Web3ゲームへの投資は、将来伸びる領域としてキャピタルゲインを狙うVCに注目されています。これまではインフラ投資が中心でしたが、Axieの成功を通じてマスアダプションには、ゲームをはじめとしたアプリケーション層の重要性が浮き彫りになったことで、Web3ゲーム投資が注目を浴びるようになりました。実際に、ゲームはブロックチェーン上で展開される可能性が高く、Web3の世界においてますます重要な役割を果たしているように感じます。
Web3ゲームの魅力の一つは、データポイントを豊富に取得できることです。コミュニティ内での意見を吸い上げてゲームに反映させることが可能であるため、コミュニティとの交流によってユーザーとの強い結びつきを形成し、アクティブなプレイヤーコミュニティを築くことができます。また、NFTを通じて得られる新たなデータポイントは、従来のWeb2企業では実現できなかったことを可能にします。例えば、購入後の利用状況や所有者の移り変わりなど、ユーザー行動のデータを取得できるようになることで、詳細なユーザーアナリティクスをもとに、個人に向き合ったサービスが提供されるようになるかもしれません。
今、Web3ゲームは、インターネットの登場時に経験したような過渡期にあります。新しい世界への移行が進む中で、失敗を通じて学び、進化し続けることが重要です。スピード感は高いものの、コミュニティと協力しながら少しずつ前進していくことで、新たなユーティリティに溢れた世界が実現されると考えられています。
Web3ゲーム領域の成長とエコシステム
Web3ゲーム領域は、2018年に投資機関であるBinanceLabをはじめとした多くのVCから注目を集め、比較的早い段階から投資が行われてきました。この投資によりWeb3ゲーム界隈のエコシステムが構築され、特にAxie Infinityの成功をきっかけに、様々なディベロッパーがこの領域に参入し、クオリティの高いWeb3ゲームが増加しています。Web2で成功したモバイルゲーム会社もWeb3ゲームに参入し始めており、盛り上がりを見せているのがWeb3ゲーム領域です。
Animocaを例に挙げると、彼らは2016年頃からWeb3ゲーム領域に投資を行い、成長してきました。今では、ベアマーケットにおいてもWeb2系プレイヤーが参加し、テンセントなどの大手企業もWeb3ゲーム領域に本格的に進出しています。これにより、今後およそ3~5年でWeb3ゲーム領域はさらなる拡大が期待されています。
Web3ゲームの成長を後押ししている要因のひとつに、マスアダプションの可能性が挙げられます。特にAxie Infinityの成功例は、Play-to-Earnモデルを通じてプレイヤーが収益を得ることができるというインセンティブが、多くのユーザーを引き寄せました。このような経済的なインセンティブにより、従来のゲームとは異なるWeb3ゲームへの関心が高まっているのです。
また、Web3ゲームに参加するプレイヤーは、プレースタイルや目的によって何種類かに分けられます。タワーディフェンスゲームを例に挙げると、自分で操作して塔を倒すことを楽しむプレイヤーもいれば、単純にサイコロを振って自動的に塔を倒す仕組みを楽しみたいプレイヤーもいる、といった具合です。こうした多様性を考慮して個別のインセンティブ付けを行うことで、様々なプレイヤーが参加しやすいWeb3の経済圏を作り出すことができるのではないか、と多くの投資家が期待を寄せています。
投資を考える上での視点
最後に、Web3ゲーム領域に投資する際に、押さえておくべき視点を考察します。
プロジェクトのファウンダーの経験:
ファウンダーが過去にどれだけ業界にコミットしているか、という観点です。ファウンダーの長期的な目標や動機、過去の経験や役割など、ファウンダーに対する目利きは非常に重要な要素です。単にテクノロジーメンバーの一員だったのか、それともプロジェクトをリードしていたのかなどを見極めつつ、ファウンダーとの長期的な関係性を重視して、そのプロジェクトに対する信頼性と実現可能性を判断していきます。
チームメンバー:
ゲーム開発は非常に難易度が高く、すべての要素を自力で作り上げることは経験や能力がないと難しいことがあります。自身だけでは不十分だと認識している場合は、優れた能力を持ったチームを組織し、適切な人材の組み合わせが成されているかも注意して見たいポイントです。
スケーラビリティとロイヤリティ:
これらはトレードオフの関係にありますが、両方を上手に活用する必要があります。伝統的なWeb2プラットフォームで成功したGAFAなどからの流入を増やすために広告を活用する方法も有効ですが、同時にコミュニティを築いて早い段階からユーザーの関心を高めることも大切です。両方の戦略を巧みに組み合わせながら拡大を図りつつ、ユーザーのエンゲージメントも高めていくことが成功の鍵となります。
IPホルダーとの連携:
IPホルダーのコンテンツを単に既存のメディアで発信するだけではなく、コミュニティを築き、ファンからの発信を通じてより広く知られる形態も考えられます。ファンとの関係性を大切にし、ファンの参加と拡散を促進することは、持続的な成功に繋がります。
ユーザーの質:
ユーザーリテンション率やユーザー獲得コスト、Life Time Valueなど、伝統的な指標に加えて、ユーザーの活発さやエンゲージメントにも目を向けることが重要です。
エコシステムの形成:
そのプロジェクトがそれぞれのカテゴリーリーダーになりうるか、エコシステムを形成する一端を担うかも大切な視点です。単に資金を提供するだけでなく、一緒になってその領域を盛り上げていくようなパートナーに投資をし、共創することを意識する必要があります。投資する側もテーブルに持ち込める価値を提供し、投資される側も相手の提供する価値を見極めることが必要です。
規制の不確実性:
プロジェクトがどの国で推進されるかによって規制の不確実性が異なるため、規制も重要な要素です。例えば、現在米国では規制面で非常に不確実性が高く、困難な状況に直面しているのに対し、EU圏では規制が次第に確定してきている傾向があります。こうした国ごとの規制状況の分析は欠かせません。
まとめ(所感)
やはりBinanceLabは流石ですね。Web2とWeb3におけるエコシステムの明確な違い、特にエンゲージメントが高い早期コミュニティの存在とその重要性に焦点を当てており、それが成功にどれだけ影響を与えるのかについて、大変勉強になりました。Animocaに関しては、自身のエコシステムを活用し、Web2企業とのコラボレーションを進める自信を持っている様子が伝わりました。既存企業とのコラボレーションが増えていることから、その姿勢が具体的にイメージできます。
また、VC側の視点では、Web3領域ではインフラへの投資だけでなく、アプリケーション層への投資が増えていると強調されていたことが印象的でした。それはマスアダプションへの鍵にも繋がるのだと。参考になる情報が満載のセッションでした。
それでは次も見てみましょう!