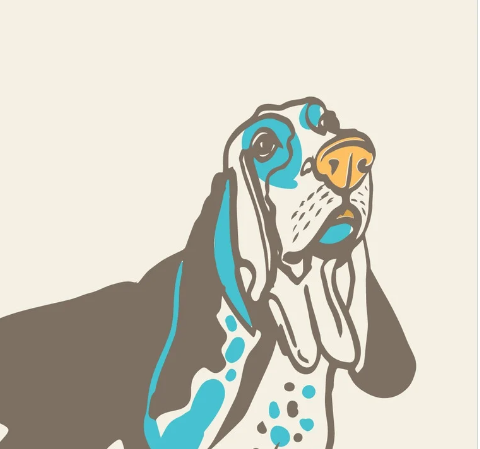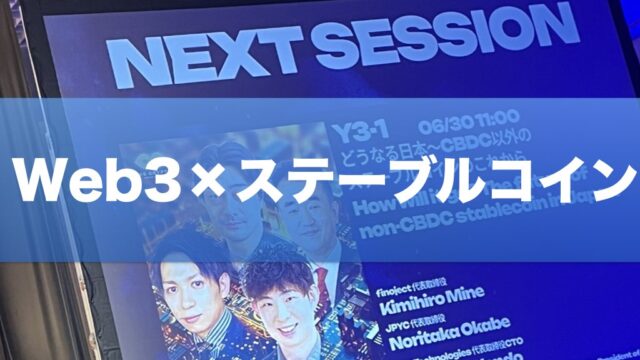2023年6月28日(水)~6月30日(金)に京都で行われた、IVS Crypto 2023 KYOTOに参加してきました。会場では、Web3や暗号資産に関連する様々な議論や催し物が開催されました。本記事では、「What’s next in DeFi?」のセッションを参考にしながら、【Web3×Defi】に焦点を当てて、Defi(分散型金融)の進化について考察してみたいと思います。
- What’s next in DeFi?(DeFiの次なる展開は?)
- Infinity Ventures Crypto, Analyst – Clement Chen氏
- Cega, Co-founder / CEO – Arisa Toyosaki氏
- Blizzard Fund/Ava Labs, Head of Research – Jun Liu氏
- Kyber Network, Founder – Loi Luu氏
Defiとは
金融とテクノロジーの融合によって生まれたDefi(分散型金融)は、伝統的な金融機関や中央集権型取引所を介さず、ブロックチェーン技術とスマートコントラクトを活用して金融サービスを提供する分野のことを指します。Defiの発展により、世界中の個人や機関がオープンかつ透明性の高い環境で、資産の取引や金融商品の提供を行うことが可能になると言われています。
ビットコインが登場してから16年の歴史を持つ仮想通貨の世界において、Defiは2018年頃に台頭しました。Defi Summerで隆盛したのは2020年と、まだまだ若い分野です。そしてこのDefiの世界は、テクノロジーを理解している人と金融を深く理解しているプレイヤーで形作られているのが現状です。
Defiにおける2種類のイノベーションって?
インフラ面でのイノベーション:インターオペラビリティ
Defi領域では最近、金融商品のトークン化について活発な議論が行われています。債券、仕組債、デリバティブ、CDSなど、実際に利用されている金融プロダクトをDefi領域で実現する可能性について、多くの金融プロフェッショナルが関心を持っています。このような中で、十分なセキュリティや信頼性を持つインフラの充実は大きな焦点となります。機関投資家など多くの金融プロフェッショナルがDefiに参入するためには、安心安全なインフラが整備されている必要があるためです。
幸いなことに、Defi領域では利用可能なプロトコルが増えてきています。アプリケーション開発キット(SDK)やアプリケーションを呼び出すインターフェース(API)も充実し、Defiのインフラが整いつつあると言えます。
Defiにおけるインフラ面でのイノベーションについて考えてみると、インターオペラリティ(異なるチェーン間の相互作用)が思い浮かびます。例えば、CatalystAMMは、異なるチェーン間でのトークンの交換が可能です。このように、近い将来、互いのチェーンを意識することなくやりとりが可能な状況になるのではないかと考えています。
金融面でのイノベーション:既存金融との接続性
Defi領域における金融面でのイノベーションは、これまでの暗号資産内でのトークン価値をベースとした金融機能からの脱却が進んでいることではないでしょうか。これまでは、主に暗号通貨間での価値交換やスマートコントラクトを活用した借貸などが主流でしたが、最近ではDefiプラットフォーム上で現実世界の金融プロダクトを実現する議論が活発になっています。
特に大きなブレークスルーとされるのは、デリバティブ(オプションや先物)や仕組債などの金融商品が、Defi領域で実現可能になりつつある点です。これにより、暗号通貨だけでなく、現実世界の資産や金融商品をDefiプラットフォーム上で取引したり、投資したりすることが可能になっています。
この金融面でのイノベーションには重要な意義があります。まず、Defiが従来の金融システムとの接続性を高めることで、より多様な金融商品を提供し、投資家やトレーダーにとって魅力的な選択肢を提供できる点です。次に、デリバティブや仕組債などの実現により、トークンの利用範囲が拡大され、デジタル資産の活用価値が向上する点です。これらにより、より効率的なリスクヘッジや運用が可能になり、新たな金融サービスの創出やさらなるユーザーの参加を促進できると期待されています。
Defiに何を求める?
UI/UX改善
Defiに求めることとして、まずUI/UX改善を挙げたいと思います。例えば、ユーザーフレンドリーで直感的な取引体験ができることです。現在、異なるブロックチェーン間でのトークンの移動には手間がかかることが多々ありますが、これをシームレスかつスムーズに行えるように改善する必要があります。ユーザーが、チェーン間の移動など複雑な手順を意識することなく、ネットワーク上でトランザクションを完了できる環境を構築することが求められます。
ウォレットの改善もUI/UX向上の重要な要素です。使いやすく、安心安全なウォレットの提供は、ユーザーの利便性を高めるだけでなく、セキュリティリスクを軽減する助けとなります。ユーザーが自分のトークンや資産を簡単に管理し、安全に取引を行えるようなウォレットの仕組みが必要です。
規制の整備
次に、規制面の整備です。Defiを語る上で規制は欠かせない要素です。少し脱線しますが、現在、Defiには主に2つのタイプが存在しています。1つはパーミッションレスなDefi。これは誰でも利用可能で、KYC(顧客の身元確認)やAML(マネーロンダリング防止)チェックが不要なものです。もう1つは、主に機関投資家を対象としたDefiで、KYCやAMLなどの規制対応が前提となっています。現在、ユーザーはこれらの選択肢から自由に選ぶことができます。つまり、規制された金融機関から提供される枠組みでの金融サービスを利用することもできれば、自由なネットワーク空間でパーミッションレスなDefiを活用することもできるというわけです。
規制の重要性に話を戻しましょう。
DeFiプロジェクトの中には、オフチェーンでの決定や中央集権的な要素を取り入れるものもあります。このような動きに対して規制当局が懸念を抱くことがあるため、多くのDeFiプロジェクトがガバナンストークンホルダーやコミュニティによる分散型の管理体制へ移行しようとする動きが見られています。そのため、規制の整備は、DeFi全体の発展にも影響を与える可能性があるとして注目されているのです。
また、機関投資家の間では、スマートコントラクトのコスト削減における有用性が理解されつつあります。例えば、これはWeb2サービスにおける事例ですが、元々紙ベースの契約で互いに資料を受け渡しながらサインをしていたものが、今ではDocuSignで対応するようになっています。同様に、近い将来にはスマートコントラクト上で透明性高く情報が互いに確認できる形でやり取りされるような未来が来るかもしれません。そして、こういった世界は、規制が正しく整備された時にこそ実行力を持つとも言えるのです。
規制とイノベーションの融合
規制には、良い規制と悪い規制があります。悪い規制とは、基準が明確でない規制です。Defi領域で起きていることを理解しない、保守的に蓋を閉めるような規制や、不確実性が残る規制は、新たなイノベーションを阻害する要因になります。一方、良い規制とは、悪意のあるプレイヤーを排除し、市場における信頼性を高めることを目指します。同時に、健全な成長を促進するための環境を整備し、優れたプレイヤーを育てる役割を果たします。グレーな領域を明確にし、市場参加者が成長しやすい場を提供するのが良い規制です。規制自体は悪いことではなく、市場の健全性を守り、投資家や利用者の信頼を築くために必要な要素と理解されるべきです。
Web2時代の良い規制の例として挙げられるのは、Communications Decency Act of 1996でしょう。この法律は、プラットフォーマーに対してユーザーの不適切な投稿に関して免責を認めるもので、ネット産業の発展を後押ししました。同様のアプローチをWeb3にも応用することで、イノベーションを促進する法制度の整備が可能だと考えられます。
規制という形で過度に締め付けるのではなく、ガイドラインを示す形式を検討してみるのも良いかもしれません。a16zcryptoが提唱するマトリスクのような枠組みを活用し、物事を明確に定義付けることで、プロジェクトの評価基準を明確化できます。これらを基準にプロジェクトを見ていくことで、プロジェクトの良し悪しが判断しやすくなることも考えられます。
Defiの成熟を目指す上で、規制は二つの側面を含む課題です。一つは、分散化テクノロジーを用いて金融機能が構築可能な環境が違法として取り締まるのか、もう一つはその機能の上での個別の振る舞いに対する事柄を取り締まるのか、という点です。イノベーションを促進しつつも、不正行為や悪意のあるプレイヤーを排除するために、メリハリを持ったフレームワークの構築が求められます。
まとめ(所感)
Defiの歴史は数年程度と浅いものの、その発展には勢いがあります(現状はまだグレーな状況ですが)。規制の整備と共に、スマートコントラクトを利用した効率的かつ高度化が可能な新たな金融イノベーションに対して、機関投資家を含む様々なプレイヤーが参入してくる様相を感じています。このパネルディスカッションではCega CEO Toyosaki氏が議論をリードしており、同じ日本人として彼女の活躍には嬉しさを覚えると共に、私も負けていられないと鼓舞されたのでありました。
続いて次を見ていきましょう!