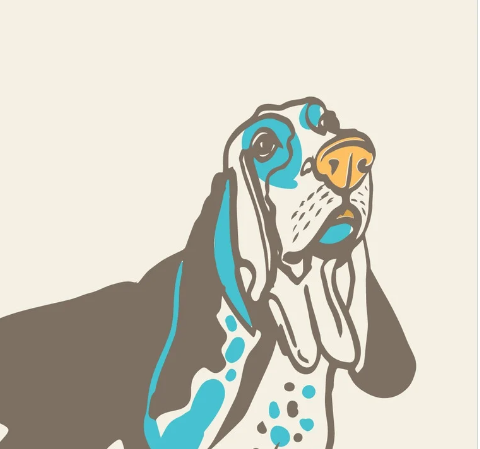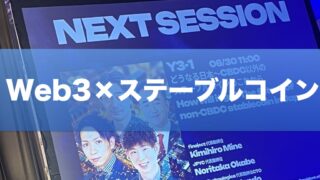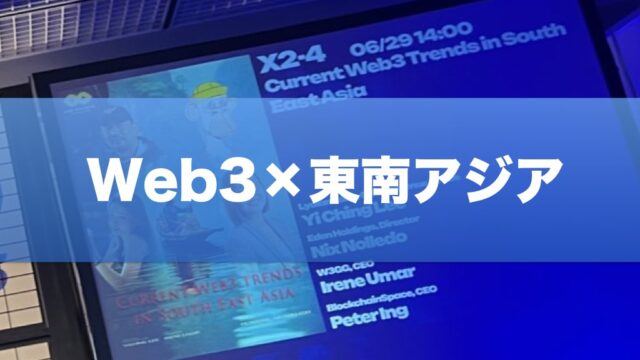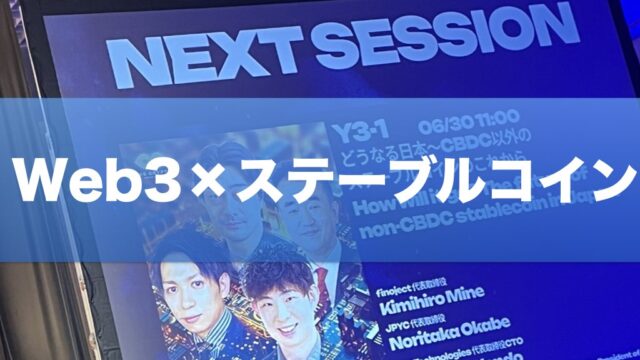2023年6月28日(水)~6月30日(金)に京都で行われた、IVS Crypto 2023 KYOTOに参加してきました。会場では、Web3や暗号資産に関連する様々な議論や催し物が開催されました。本記事では、【Web3×マーケティング】に焦点を当てて、Web3マーケティングの展望について考察してみたいと思います。
- みんなどうやっている?Web3業界におけるマーケティング手法を語ろう
- Ernst & Young ShinNihon LLC – Masahiro Takeda
- FUELHASH, CEO – 紺野 勝弥氏
- SUSHI TOP MARKETING, CEO – 徳永 大輔氏
- 和らしべ CEO – 井元 秀彰氏
Web3マーケティングの特徴とは?
Web3マーケティングの登場
Web2領域でのマーケティングにおいては、GoogleAnalyticsなどの分析ツールを用いてターゲットを選定し、効果的な広告戦略を立てることが一般的でした。昨今、Web3領域ではNFTを活用した新しい手法が注目を集めています。企業やプロジェクトがNFTを利用したマーケティングを行う際の手法について見てみましょう。
まだ手探りの状況ではありますが、今界隈で進められているのはNFTの配布によってウォレットアドレスにマーキングを行い、それらのアドレスを対象に次の施策を展開すること。保有者が持つNFTの情報や所有権に基づいたターゲティングができるようになるため、より個別化されたマーケティングが実現すると期待されています。
また、企業間でブロックチェーンのインフラ面を共有化し、アプリケーションの部分で差別化を図るコンソーシアムの例も観察されています。これは、既に構築された仕組みをコンソーシアムの参加者が共有化することで、各企業がアプリケーションに特化して取り組むことができるというメリットがあります。
データの公共性と秘匿性とのバランス
しかし、Web3マーケティングは、まだWeb2のような成熟した手法には達していないのも現状です。特にNFTを活用したマーケティングでは、ターゲティングに必要な情報がWeb2のように豊富に得られておらず、保有者のNFTに関するデータの正確性や信頼性の確保、プライバシー保護が課題として掲げられています。これらの課題に対して、現在Web3の領域ではまさに模索が行われている段階であり、新しいテクノロジーやプロトコルの開発、データのブロックチェーン上での管理手法の改善が進められています。NFTの持つ不可逆性やオリジナリティを活かし、独自のブランド価値を築くことが重要な戦略となりそうです。
2024年以降のマーケティング戦略
2024年に、マーケティング領域では大きな転換期が訪れると言われています。それは、Google等のプラットフォームによる3rd Partyデータを用いた広告が制限されることです。これは、これまで利用していたTwitterやFacebookなどの情報を使ったターゲティング広告が難しくなることを意味し、B2C企業(例えばアパレル関連の企業)などにとって大きな困難になることが予想されています。この規制はGDPR(一般データ保護規則)などの個人情報保護規制と関連しており、企業は今、こぞって自社顧客データの整備に力を入れているのです。
3rd Partyデータを用いた広告が制限されるというのは、そういった広告がうてなくなるってことだよ!
こうした状況において、NFTを活用したデータ検索のアイデアが登場しています。例えば、自社が作成したNFTを顧客のアドレスに送付することで、そのウォレットが他にどのようなNFTを持っているのか、どの程度のトークンを保有しているかなどの資産情報を把握できます。自身のNFTを介して、個人情報を守りつつ、他の情報からウォレットの保有者の特性を推測することも可能となります。このアプローチを「トークングラフ」と呼んでおり、1対1の個別コミュニケーションを実現する可能性を秘めています。個人情報を守りながらも、お客様のデータ解像度を向上させ、より質の高いコミュニケーションを提供することが期待されています。
大企業のWeb3参入の背景と事例
Web3領域参入の目的
このような環境下で、スタートアップ企業に限らず、数々の大企業がNFT領域に参入し始めています。ここでは、その背景に考えを巡らせてみましょう。
まず、NFTを活用する大きな魅力の一つに、新しい顧客タッチポイントの創造が挙げられます。大手企業がNFTを活用することで、通常ターゲットになっていなかった若い世代など新たな層の購入者を取り込むことができます。例えば、特典としてゲームのNFTを付与することで、若い世代を中心に商品購入のインセンティブが高まり、新しい顧客層の獲得につながることがあります。
さらに、NFTを活用することでロイヤリティの可視化が可能になります。従来のB2C企業では、ロイヤリティの高い顧客の特定や継続的なエンゲージメントの測定は難しいとされてきました。しかし、NFTを利用することで、ユーザーのアクティビティをブロックチェーン上で記録し、継続的なエンゲージメントの高い顧客を特定することができます。これにより、個人情報を侵害せずにロイヤリティの高い顧客を把握し、より効果的なマーケティング戦略を立てることができるようになるのです。
大企業がNFTを活用するもう一つの魅力は、顧客のさまざまな面や行動を網羅的に把握し、全体的な顧客層を見逃さずにターゲティングできる点です。従来の方法では、顧客の様々な情報を異なるデータベースやシステムで管理していたため、異なるアクティビティの内容を同一フォーマットで整理することは困難でした。例えば、顧客のオンライン購買履歴とSNSでの活動履歴は異なる形式やプラットフォームで生成されるため、それらを一つのデータベースに統合することは、非常に骨が折れる作業です。しかし、NFTを利用することで、ブロックチェーン上で顧客の行動履歴やアクティビティを記録し、それらを統一的に管理できます。これにより、顧客の行動やニーズをより網羅的に分析できるようになると考えられているのです。
事例:NFTを活用したGamefiギルド
続いて、実際にNFTを活用しているプロジェクトや企業の取り組みを見てみましょう。
Gamefiギルドは、プレイヤーが遊んで報酬を得ることができる「PlayToEarn」ゲームにおいてNFTを活用したマーケティング戦略の一例です。このギルドは、ゲーム内でトークンを獲得できる仕組みを提供しており、プレーヤーは、強力なキャラクターのNFTに投資したり購入したりすることで報酬を増やすことができます。
ギルドは高価値のNFTを購入し、優れたプレーヤー(スカラー)に対してそれらを貸与したり、エアドロップなどの特典を与えたりすることで、ゲームクリアの成功率を高め、報酬を増やします。このGamefiギルドは、プレーヤーが共同の目標を達成することを目指すコミュニティとして機能しており、ゲーム内での競争や協力が活発化していきます。
事例:ロイヤリティマーケティングとNFTの融合
2021年10月頃には、NFTを使ったマーケティングのコンセプトはまだ実験的で、小規模な試みでした。例えば、資生堂のイギリスでは一定金額を支払った顧客にNFTを配布し、試供品などを提供することで顧客の関心を引こうとした試みは、その一例です。しかし、2022年9月頃になると大手企業もNFTを活用し始め、ロイヤリティマーケティングという形で活用されつつあります。これは、顧客の忠誠心を高めるために、顧客に特典や特別な体験を提供することで長期的な関係を築く方法です。NFTを用いることで、ポイント活用などと似たロイヤリティマーケティングが進化し、よりパーソナライズされたサービスを提供できるようになります。
例えば、百貨店は富裕層向けの外商の集合体であり、従来は個別の提案によって顧客にサービスを提供していましたが、経済成長により一般の人々も裕福になったことで、広く一般向けの商業施設として変貌しました。しかし、近年では再び個人向けの営業に回帰する動きが見られます。これには格差の拡大や多様なニーズの増加などが影響しており、画一的な商売が難しくなっていることが要因として挙げられます。このような状況で、NFTが顧客と効果的なコミュニケーションを行うためのツールとして注目を集めています。NFTは顧客とのコミュニケーションをよりリッチで視覚的なものにできるため、顧客の多様なニーズを汲みとり、強い結びつきを築き上げるために有効だと期待されているのです。
また、NFTを活用したロイヤリティマーケティングの成功例として、「Not A Hotel」も注目に値します。「Not A Hotel」は、Web3領域の顧客に注目し、斬新で高価な体験価値を提供するためにNFTを活用しました。彼らはNFTをツールとして用いることで、価格の上昇や転売への魅力、お客様の体験価値向上などを追求しました。ここで最も重要な点は、デジタル化されたホテル空間でしか実現できない、これまでにない体験価値を提供したことです。その体験が顧客の本質的なニーズであり、NFTを効果的に活用するための土台となりました。
全員がウォレットを持つ時代は来る?
近い将来、全員がウォレットを持つ時代は来るのでしょうか?
そのような世界線が現実になる可能性は大いにあり得ると考えられます。仮想通貨だけでなく、自分が好きなNFTなどを管理する手段として広く普及するかもしれません。さらに、未来のメタバース・マルチバースの世界では、ウォレットが当たり前のように使用され、クレジットカードや現金などの従来の支払い手段が意味をなさなくなる可能性もあります。
安全性やマネロン対策などの課題はある反面、「作る」という点において、ウォレットは数分で作成することができ、銀行口座よりもはるかに迅速で簡単です。このことからも、何らかのきっかけで一気に全員がウォレットを持つ世界線が到来することは想定しうる未来だと考えられます。
ウォレットの爆発的な普及のきっかけになりうる現象として、「NFTマーケティングの費用対効果が明確にされること」と、「ウォレットの保有率が特定の水準を超えること」を挙げたいと思います。まず、NFTマーケティングにおける費用対効果については、現時点では過去の実績が不十分です。しかし、事例が増え、統計的な意義が明確に示されれば、NFTマーケティングは急速に普及する可能性があります。実際の成功事例が積み重なり、その効果を統計的に裏付けることで、NFTマーケティングが広く認知され、広がりが加速する未来が考えられます。次に、ウォレットの保有率に関する3.5%ルールという理論があります。この理論では、コミュニティ内でウォレット保有率が一定水準(具体的には440万人)を超えると、一気に拡大していくのではないかと考えられています。このようなウォレット保有率の急増が起きるタイミングで、ウォレットとNFTの普及が大きく変わるかもしれません。キラーコンテンツとなるアプリケーションやステーブルコインの普及などがポイントになると考えています。
まとめ(所感)
現在、GDPR規制により3rd Partyデータの利用が制約される中で、個人情報の侵害を避けつつも解像度の高いデジタルマーケティングやロイヤリティマーケティングを進める方法として、NFTの活用は非常に有望だと感じました。現時点ではノンカストディアルなウォレット(Metamaskなど)の普及率はまだ数パーセントに過ぎません。しかし、3.5%理論で言われているように、キラーコンテンツやステーブルコインの広がりにより、ウォレットの普及率が一定値を超えると、一気にマスアダプションが達成される可能性を感じます。まだまだこれからという状況ですが、この時代の過渡期に何をするか、どう行動するかで次の時代の主役になれるかが決まる気がしました。
次も見ていきましょう!