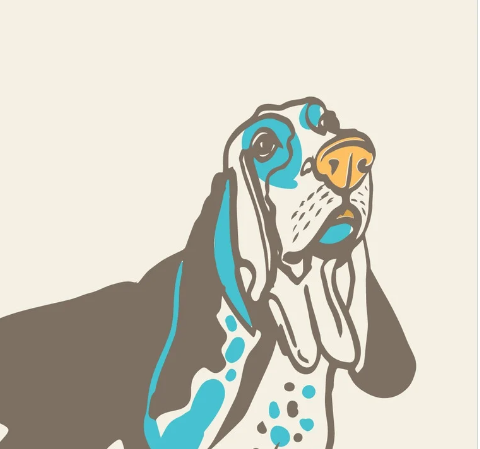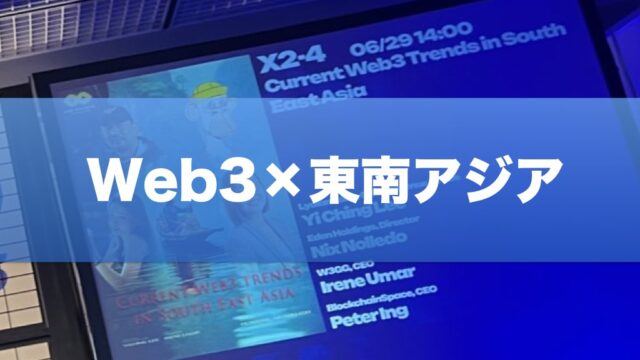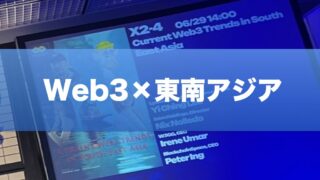2023年6月28日(水)~6月30日(金)に京都で行われた、IVS Crypto 2023 KYOTOに参加してきました。会場では、Web3や暗号資産に関連する様々な議論や催し物が開催されました。本記事では、【Web3×女性リーダー】として、女性の視点から眺めたWeb3のトレンドと未来について、キーワードごとにまとめてみたいと思います。
- Rise of Women in Web3
- Tess Ventures, Founder – Tess Hau氏
- Curious Addys, CEO – 秋吉真衣氏
- CoinDesk Japan, CEO – 神本 侑季氏
- Ocular Fund, Lead – Amy Zhao氏
- Observation by Female Founders in Web3: The new trends and new hope/Y3-4 Web3女性起業家の洞察による、今注目すべきトレンドと今年の展望
- HONEYCON/Web3Girls, Founder – Web3honey氏
- Binance Japan/SEBC 取締役 – 山本 仁美氏
- HIKKY, COO – さわえ みか氏
- Pivot Tokyo Director – 満木 夏子氏
- Looking at Web3 Market and Future from Females’ Point of View/Z3-6 女性の視点で探るweb3マーケットと未来
- HONEYCON/Web3Girls, Founder – Web3honey氏
- KawaiiGirlNFT, Founder – Ame-Chan氏
- Oasys, PR&Communication Manager – Akari Oeda
- The Fabricant, Community Manager – Kay氏
日本におけるWeb3
現状:日本の暗号資産市場の有望性
2022年は、暗号資産市場にとって激動の年でした。ビットコインは、高値から約380万円の下落を経験し、2018年以来の長い下落トレンドが続きました。2023年の四半期には時価総額が前年比83%増加し、一度は回復を果たしたものの、最近ではアメリカのSEC(証券取引委員会)の動向が市場に大きな影響を与えており、市況はあまり良くないと言われています。
そんな世界市場の不安定さとは対照的に、日本では暗号資産市場が順調に推移しています。規制面でのサポートの充実や市場の安定性がプロジェクトを進めやすい環境を作り、多くの企業が日本を拠点として選び、本社の移転やベースの構築について相談を持ちかけられるようになっているのです。
アジア全体で見ても、日本を含む地域は暗号資産市場の成長が非常に有望だと考えられています。日本の規制当局の前向きな姿勢により、新しいプロジェクトの展開や技術の導入がスムーズに進んでいるためです。特に仮想通貨の文脈では、日本は2017年に資金決済法を改正し、法整備を早くから進めてきた国として知られています。アメリカやヨーロッパではマイカー導入に関する取り組みが進んではいますが、それにはまだ時間がかかると見込まれており、日本を有利な立ち位置に押し上げています。
また、中でもステーブルコインの動向は注目に値するとされています。今年(2023年)の6月に資金決済法が改正され、ステーブルコインの流通や発行に関する基盤が整えられている状況が後押しし、今後さまざまな事業が参入してくることが期待されています。Web3は単独で成長していくのではなく、既存のコミュニティを取り込んでいくことが成長の重要な要素です。暗号資産のボラティリティは大きな課題ですが、価格の安定したステーブルコインは、リアルなエコノミーとWeb3を結びつける重要な役割を果たすだろうと期待されているのです。
課題:Web3リテラシーと教育の充実
課題として意識を傾けるべきポイントは、ブロックチェーン技術がマスアダプションを遂げる中で、人々が無意識に利用出来る環境が整うことで、ブロックチェーンや暗号資産に関する理解が不足している人が増えているとの指摘があります。これまでは、単に新しい技術を使用すること自体に価値がありましたが、現在はその技術を活用してどのように新しい価値を生み出すかが重視されています。ブロックチェーン技術の活用が当たり前の世界に変わりつつある中、ブロックチェーンを使う意義やリスク、責任についての議論は軽視されてはなりません。簡単にアクセスでき、ブロックチェーンの壁を感じさせずに使用できることはもちろん重要ですが、同時にWeb3のリテラシーや教育の充実の重要性が増してくる、そして増していくべきであると唱えられています。
大企業の参入
現状:Web3に特化したチームの登場
昨今、多くのグローバル企業が、Web3に特化した責任者を任命することでWeb3領域に参入してきています。Web3に精通した経営層が少ない中、社長の直属で専門的なチームが作られるようになっています。これは、業界のサステナビリティや製品のトレーサビリティを考慮する際に、ブロックチェーン技術が不可欠であるという認識が広まっているためです。かつては外部委託が主流だったWeb3の領域も、企業がインハウスで積極的に取り組むように変わりつつあり、専門のチームを組織するための採用活動も活発に行われています。グローバルな求人情報を見ても、こうした動きは顕著であり、今後これらの取り組みがどのように進展していくのか、非常に注目されるところです。
課題:Web3の導入戦略とコミュニティ運営
B2C企業の事業の目的は、お客様にサービスを提供することにあります。Web3に関心のある若い世代だけでなく全ての人にサービスを届ける必要があるため、新しい技術に慣れていない人々向けの登録作業の改善などに時間がかかり、コンテンツの開発にまで手が回りにくいことがよくあります。そのため、大企業がWeb3に参入する際には、一般ユーザーにとって使いやすいUIやインフラの改善が非常に重要になります。
また、多くの企業がコミュニティ運営に頭を悩ませています。Web3のプロジェクトには、投機的な動機だけで関わる人が多いため、利益が得られなくなるとすぐに参加者が減ってしまいがちです。さらに、NFTなどのプロダクトは、バリューが一定以上ないと価格も下がってしまう傾向があるため、企業のブランドを背負った取り組みは難易度の高いものとなります。Web3は最先端の技術でありますが、その技術を使うのは人間です。そのため、Web3コミュニティを運営する際には、その先に人間がいることを考えながらニーズや視点を捉え、単にサービスの提供にとどまらない戦略まで考えること、そして、サービスやプロダクト自体のファンを増やすなど、コミュニティンの存続に注力することが必要不可欠です。長期間コミュニティを盛り上げ続けるのは至難の業ですが、プロジェクトの中長期的な継続を示すロードマップを作成したり、ユーザーが一度離脱しても戻ってきて参加できるような安心感を持つコミュニティ形成したりすることが大切です。
クリエイターエコノミーの発展
現状:新たなカルチャー創出とリアル世界への干渉
Web3のコンテンツを生み出す、クリエイターの視点からもトレンドを眺めてみましょう。実は、数年前から3Dモデルの売買によるクリエイターエコノミーの文化が盛り上がりを見せています。ブロックチェーン技術の活用はまだ進んでいないものの、面白く斬新なアイディアが次々と生まれており、それらにブロックチェーンを後から組み込むことが出来るのではないかと期待されています。
数年前までは、「現実世界に存在する身体を元にアバターを作る」という作業はとても手間がかかるものでしたが、現在はアバターが溢れかえるほどの状況になっています。そして、これらの豊富なコンテンツ、つまりアバターや次世代モデルを使って、音楽や芸能などに特化したイベントを作り上げ、自分たちで新しいカルチャーを創出することがトレンドとして人気を集めています。例えば、音楽フェスや劇団のように特定のテーマに焦点を当てたニッチなイベントの開催です。また、アバターネームを作成することで、現実世界とは異なる人格を持つことも可能です。例えば、経営者として日々の仕事をする一方で、バーチャル空間ではクリエイティブなカルチャーを生み出す立場になり、自由な創作活動を楽しむこともできる世界になっているのです。
最近では、バーチャル空間からリアルな世界に干渉する取り組みも増えてきています。この融合から生まれる新しいカルチャーが非常に面白く、ビジネス的な視点にとらわれないアイディアの種の宝庫だ、とクリエイターの間で注目を集めています。NFTなど単にWeb3関連の技術を使ったプロジェクトを行うことよりも、企業が抱える課題に対して、新しいアイディアをもとにWeb3の技術を適用するアプローチを考えることがポイントになりそうです。
課題:魅力的なコンテンツ作り
一方で、暗号資産を持ったとしても、それを面白いと感じられなければユーザーは離脱してしまいます。単に仕組みを構築するだけでは人々は定着せず、魅力的なカルチャーが育まれないというケースはよく見られます。だからこそ、コンテンツの面白さに注力することが今後の成長に不可欠であり、そのための環境を整えなければならないのです。現代は、個々の人がみなクリエイターとして活躍できる時代だと言われています。彼らがSNSやバーチャル空間で盛り上がり、面白いコンテンツを提供し、そこに人が集まることでさらに盛り上がる場を創り出す、といったポジティブな循環を生み出すことで新しいカルチャーは生まれまていきます。
個別市場の動向
NFT:市場における三つの山
NFT(非代替性トークン)は数年前まであまり馴染みのない言葉でしたが、現在ではSNSなどでよく耳にするようになってきました。特に直近2年間のNFTの取引量は急速に増加し、知名度と規模の両面で大きく拡大しました。まず、市場が特に盛り上がった「三つの山」に触れながら、この数年間の概要をさらってみます。
NFT市場は、2021年の初めに多くのコレクターやアーティストが新しいアートの販売形式として注目し始めたことで急成長しました。一部のNFTが高額な取引価格で売買されたことでNFT市場に興味を持ち始めた人も多いかもしれません。特に、2021年3月には、Beepleが制作した「Everydays—The First 5000 Days」が6900万ドル(約75億円)で取引され、これをきっかけにNFTへの注目が爆発的に高まりました。
その後、2021年8月頃には有名なBlue Chip(ブルーチップ)NFTプロジェクトがローンチされ、NFTバブルのような状況が訪れます。この頃には、国内でもNFTという言葉が徐々に台頭し始め、NFTの存在が一般的にも知られるようになっていました。
そして2021年の9月から2022年の初頭には、NFTプロジェクトの中で注目を集めていたクローンエックスの発行元ブランドであるアーティファクトが、ナイキによって買収されるという大きな話題がありました。NFTがアニメやゲーム関連で注目されるようになったのもこの頃で、NFTには「第二の山」と呼ばれる成長期が訪れました。NFT自体が一般的に馴染みやすい存在になってきた時期がこの頃です。
「第三の山」は、2022年の4月頃から始まったサイドバブルのような状況です。これは、ムーンバードというNFTプロジェクトが驚異的な売上を記録し、たった2日間で約330億円の売上を達成した出来事をきっかけに引き起こされました。しかし、その後、2022年後半からは取引量が大幅に減少し、バブルから一息ついて落ち着いてきたのが直近のマーケット状況です。取引量が落ち着いてきたとはいえ、NFTの技術自体は着実に発展しています。NFTはアニメ、ファッションブランド、スポーツ、音楽など、さまざまな領域で応用が進んでおり、デジタルアート以外の分野でも注目を集めています。2022年時点ではNFT市場の規模は約30億ドルと言われていますが、今後5年以内に約136億ドルにまで成長するとの見方もあります。
NFT:市場の安定的な発展を促す要素
NFT市場に限らず、ブロックチェーン全体の課題として、ボラティリティの高さや参入障壁の高さが挙げられます。この課題を克服し、安定的な発展を実現するためには、ブロックチェーン技術そのものの発展とそれを活用した技術が広く浸透していくことが重要です。特に後者においては、2つのポイントが挙げられます。
一つ目は、利用者の数を増やすことです。現存するNFTプロジェクトの多くが、コミュニティ文化の上に成り立っています。NFTのプロジェクトは様々な形態がありますが、今取引量の多くを占めているのは、ジェネラティブNFTと呼ばれる、背景や顔などのパーツをコンピュータで組み合わせて自動生成する技術です。これにより万単位のイラストが簡単に作成できるようになりました。NFTを持っているホルダーや欲しいと思う人々の中で、コミュニティが形成されることで、作品の魅力を広める好循環が生まれています。これにより、利用者数が増える効果があり、利用者数の増加という面においてNFTプロジェクトは大きな役割を果たしています。
二つ目は、利用する機会を増やすことです。NFTの技術は、デジタルアートだけでなく他の分野でも広く活用されているため、今後日常的に触れる機会が増えることは確実です。例えば、ブロックチェーンゲームやデジタルとリアルを組み合わせたプロジェクトが活発に展開されていることは、この好例でしょう。また、ライブチケットやコミュニティ権利の利用にもNFTが導入されており、SBT(Security Token Offering)という仕組みも注目を集めています。これらの動きによって、NFT市場はコミュニティ文化を基盤にして様々な領域の市場と融合し、確実に成長していく領域であると言われています。
ブロックチェーンゲーム:Play-to-Earnがもたらした爆発的な成長
ブロックチェーンゲームは、2018年から2020年までの2年間で驚異的な成長を遂げました。ユニークアクティブウォレット数は約350倍にも増加し、特に東南アジアを中心に、Play-to-Earn、つまりおこづかいを稼げるという文脈で人気を集めました。現在は成長ペースは落ち着いていますが、各国の事業者は依然としてブロックチェーンゲームに注目しています。
ブロックチェーンゲームが注目される理由として、既存のWeb2のソーシャルゲーム市場が成熟し、開発費が巨額に膨れ上がっていることが挙げられます。50億円、ものによっては100億円もの開発費を要することも多い中、中国の資本が参入してさらに競争が激化している状況を受けて、新しいブロックチェーンを用いたWeb3ゲームが突破口として見出されているのです。
ユーザー側から見てもブロックチェーンゲームはとっつきやすく、ウォレットやゲームを通していつの間にかブロックチェーンに触れている人も増えています。特にPlay-to-Earnモデルの登場により、ブロックチェーン全体で相当数のユーザーが増えており、今後もマスアダプションにあたってブロックチェーンゲームが大きな鍵を握っていると考えられています。
ブロックチェーンゲーム:ファンコミュニティとの共創に向けて
ブロックチェーンゲームは、現在エコシステムを拡大する流れにあります。今後、さらに人気のIPが参加したり、大手企業が参入したりすることで、ユーザー数の増加が期待されています。ここまで注目が集まっている理由は、市場の成熟に加えて、ゲーム開発の考え方や方法が変化していることが挙げられます。
従来はプロダクトアウト型の開発が主流でしたが、現在の厳しい市場状況の中で、コミュニティを中心にゲームを作っていくアプローチ:まずファンコミュニティがあり、その周辺にプロダクトが形成される開発方法が浸透しつつあります。ブロックチェーンやWeb3はファンコミュニティとの親和性が高く、ユーザー主体の思想を重視することから、こうしたアプローチとの相性が良いのです。
現在多くの企業がこの分野に注目しており、大手事業者の参入が予測されています。今後ますますユーザーの裾野が広がり、ファンコミュニティとの結びつきを強化しながら、市場が発展していくだろうと考えられています。
メタバース:未来のエンターテインメント市場
メタバースという言葉は最近よく聞くようになりましたが、実はそのコンセプトは18世紀頃から存在していたと言われています。2021年10月にFacebookがリブランディングでメタ社になると発表したことや、2022年の2月頃には平均取引価格がピークを迎えたことなどを受け、ようやく私たちが楽しむことができる段階になりつつあります。
しかし、完全なメタバースにたどり着くには、人件費や技術の面でまだまだ時間がかかると言われています。メタバースの価値や可能性、利用方法について試行錯誤しながら、どんなイベントを開催すればより盛り上がるのか、どのようなクリエイターを招待すれば魅力的になるのかなどを検証し、メタバース内のコンテンツやエンターテインメントの向上に向けた努力が進んでいます。
企業視点では、技術の急速な進化に注目が集まっています。例えば、Apple Vision Proの発表は大きな話題となり、その活用方法やARアプリの開発について活発に議論されています。他の分野と同様にメタバース関連も、シームレスかつ先進的な技術の活用が企業にとって重要な勝ち筋です。メタバースをビジネスの一環として捉え、市場にいち早く参加し、適応していくことが重要とされています。
一方、ユーザー目線では、仮想空間でのイベントが話題を呼んでいます。海外では既に数え切れないほどのメタバース上でのイベントが開催されており、DJがスクリーン上で演奏し、参加者はグッズウェアラブルを身に着けて、クラブのような感覚で楽しむことが普通になってきました。このようなメタバースでのエンターテインメントはカルチャーとして確立されつつあり、帰ってきたくなる場所づくりが重要な要素として注目されています。また、Web2企業とのタイアップもメタバースに新たなビジネスの可能性をもたらしています。キャッシュポイントの創出に課題があるメタバースですが、イベントや商品のPR、広告など、Web2企業との協業によりリアルなビジネスと連動させる事例も増えており、新たな市場の拡大が進んでいます。
まとめ(所感)
激動の2022年を経て、市場が落ち着きつつある現在の暗号資産市場。そんな中、日本の暗号資産市場は比較的順調に推移し、規制面でのサポートや市場の安定性が外国企業の進出を後押ししています。また、Web3技術も着実に進化し続けています。ブロックチェーン技術の重要性の浸透を受け、多くの大手企業が専門的なチームを組織してWeb3領域に参入し始めています。ビジネスとクリエイティブの融合が進むことで、今後、斬新なビジネスモデルやサービスが生まれてくるのではと期待に胸を躍らせる思いです。
2023年は、暗号資産市場やWeb3領域がさまざまな転換点を経て、成長機会を迎える年となるのではないでしょうか。市場参加者として、アンテナを高く張って引き続き動向を追っていきたいと思います。
続いてはこちらです!