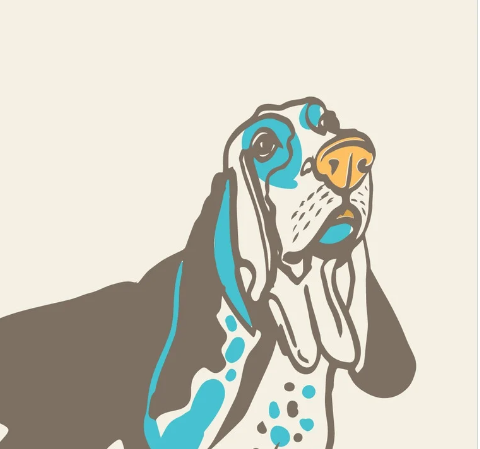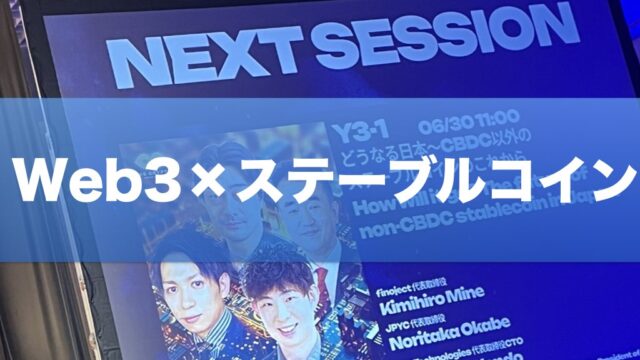2023年6月28日(水)~6月30日(金)に京都で行われた、IVS Crypto 2023 KYOTOに参加してきました。会場では、Web3や暗号資産に関連する様々な議論や催し物が開催されました。本記事では、【Web3×GameFi】に焦点を当てて、トレンドを追ってみたいと思います。
- GameFi 2.0 – What’s Next after Play to Earn(GameFi 2.0 – Play to Earnの次は?)
- Foonie Magus/ Apeiron NFT, COO – Orange See氏
- Sky Mavis / Axie Infinity, Co-founder – Jeffrey Zirlin氏
- MixMob, CEO – Simon Vieira氏
- Genopets, CPO – Benjamin Tse氏
- Laguna Games/ Crypto Unicorns, Governance – Nanessa Dimaano氏
Play To Earnゲームとは?
Play To Earnゲームとは、その名の通り「遊んで稼ぐ」という考え方にもとづき、ゲームをプレイしながら仮想通貨を稼ぐことができるゲーム形態です。遊ぶことのみを目的とした従来のゲームとは異なり、ゲームを楽しむだけでなく、実際の経済的報酬を得ることができることが大きな特徴です。このコンセプトは、ブロックチェーン技術の進化とNFTの登場によって生まれました。
Play To Earnゲームで稼ぐ仕組みについて、最も一般的な方法は、ゲーム内でさまざまなクエストやミッションをこなすことで仮想通貨やNFTといったデジタルアセットを獲得し、それを現実世界での価値に転換することです。これらは外部のプラットフォームで利用することもできるため、他のプレイヤーやコレクターと取引したり、現実通貨に変えて利益に変えたりすることができます。もちろん、ゲーム内のアイテムやキャラクターの所有権として利用することもできます。
また、他のプレイヤーとのトーナメントや対戦を行うことで報酬を得ることもできます。特にeスポーツの盛り上がりにより、トーナメントやイベントの報酬が増加しており、賞金や特別なNFTの獲得を狙うプレイヤーも増えています。
NFTが持つアイデンティティと称号の価値
ゲームはプレイヤーにとって、一種のアイデンティティになります。どのゲームをどれだけプレイしたか、好きなゲームの種類、過去のプレイ経験などの情報を通じてプレイヤー同士が互いに繋がり、コミュニケーションを楽しむこともできるようになってきました。ゲームは個々の特徴やプレイスタイルを反映するため、プレイヤー同士が共通の興味を持つきっかけとなり、新たな友情やコミュニティが生まれています。
また、ゲームのプレイ記録はNFTとして保持されますが、NFTを保有するウォレット自体が取引されることもあるかも知れません。例えば、複数のゲームで優勝したという称号を持つウォレットが高額で取引されることも考えられます。これは、ゲームでの実績や称号が価値を持ち、新たな経済的なインセンティブが生まれるということを意味します。今後、プレイヤーは自らのスキルや成果を証明する手段としてNFTを持つようになるかもしれません。
加えて、ゲームをプレイすることで成績がNFTとして記録され、そのNFTがVoting Right(投票権)に利用可能なケースも想像されています。このようなVoting Rightが高値で取引される可能性もあります。
GameFi発展におけるポイント
プレイヤーの感情に訴えるゲーム設計
ブロックチェーンゲームが長期的に流行するためには、ゲーム設計がプレイヤーの感情に訴えるものであることが重要です。つまり、プレイヤーが勝ちたくなるような仕組みや魅力的な要素を盛り込み、資金と時間を費やしたくなるような要素を取り入れなければなりません。
例えば、Play To Earnゲームには、自動的に進行するゲームとスキルを磨くゲームの両方が存在します。自動的に進行するゲームでは、プレイヤーはボタンを押すだけで進行し、手軽に楽しめます。一方、スキルを磨くゲームでは、プレイヤーが自身のスキルを駆使して勝利やランクアップを目指します。どちらに魅力を感じるかは個人の好みによるため、幅広いゲームタイプを提供することが重要です。
Web2ゲーマーの取り込み
Web2のゲーマーをWeb3に引き込むためには、上記のように魅力的なゲームを提供して彼ら / 彼女らの心を掴みつつ、ゲーム内で特定のNFTを保有しているとプラスの効果が得られるなど、インセンティブを与える必要があります。例えば、NFTを保有しているプレイヤーに対して、特別なアイテムやキャラクター、スキンなどのゲーム内コンテンツを提供する「ゲーム内での特典」や、NFT保有者だけが参加できる限定イベントやコンテンツへのアクセス権を付与する「ゲーム外での特典」、プラットフォームの意思決定に参加する権利を持つガバナンストークンの提供、などの手段が考えられます。Web3ゲームに積極的に関わる動機を与えることで自然にWeb2からの移行を促し、利用者の拡大を狙います。
eスポーツの盛り上がりも重視
eスポーツの盛り上がりも無視できない要素です。今ではeスポーツ観戦者は約7億人いると言われており、自身でプレイするだけでなく、そのやり取りを見て盛り上がる参加者も増加しています。プレイヤー自身が熱くなれることはもちろん重要ですが、周りのエコシステムの成長とコミュニティの拡大も考慮する必要があります。
コミュニティ構築
コミュニティを適切に構築することは、ゲームの経済圏の持続的な成長のために不可欠です。そのため、コミュニティのメンバーが単にゲームをプレイするだけでなく、積極的にゲームに対してフィードバックやアイディアを共有できる体制を整えることが大切です。例えば、プロトタイプを2つ用意してコミュニティにプレイしてもらい、その感想や意見を収集します。そして、得られた結果を考慮して実際のゲームに組み込むことで、コミュニティの意見を反映させることができます。このように、フィードバックを活用してゲームの改善に取り組みながら、コミュニティと密接な連携を築くことは、ゲーム経済圏の持続的な成長にとって大きな意味を持ちます。
どうなる?GameFiの今後
チャットアプリのWeb3化
次に注目を集めるだろうと期待されている形態として、まず、チャットアプリによるWeb3化が挙げられます。韓国のKAKAO、日本のLINE、中国のWechatなど、各国で人気のあるチャットアプリがWeb3に統合されることで、グローバルで繋がる新たなビジネスエコシステムが形成される可能性があります。これにより、Web3を通じた規格統一と更なるグローバル化の進展といった、ビジネス界における新たな展開が見えてきます。
日本のIPの広がり
日本のアニメや漫画などの知的財産(IP)は新興市場で非常に人気があります。特に、One Piece、進撃の巨人、ドラゴンボールなどの作品は大人気です。また、Play to Earnの代表的なプロジェクトであるAxie Infinityが人気を集めているのは、フィリピンやメキシコなどの南アメリカの新興市場です。これらの地域で日本のIPを持つ企業のゲーム開発に大きな注目が集まっていることを考えると、日本のIPの広がりは今後大きく加速するのではないかと考えられます。
仮想通貨の経済圏拡大
仮想通貨の経済圏は、今後ますます大きく拡大することが予測されます。近い未来に、Bitcoinの現物ETFが承認されると、既存の金融市場から資金が流入するだろうと考えられています。これにより、Bitcoin自体への資金が増え、さらにその後、アルトコイン(Bitcoin以外の仮想通貨)にも資金が流れます。特に、EthereumやPolygonなどの通貨が注目され、高価なNFTの購入に使われる可能性は高いと考えられます。
まとめ(所感)
Gamefiの流行には、まず、ゲーム自体が面白く熱狂的になれるものである必要がありそうです。そして、コミュニティを通じてNFTなどを活用し、ゲーム開発や運営に参加できる仕組みを構築することが肝となるでしょうか。
日本のIPは、現在GameFiが浸透している新興市場で人気があり、日本企業がWeb3領域でGameFiを展開すれば瞬く間に広まる可能性があります。さらに、2024年にはビットコインの半減期が控えており、現物ビットコインETFの承認が実現すれば、キャズムを超えて一気にマスアダプション化する未来もあり得るのではないかと感じました。GameFiの普及と仮想通貨市場の成長から目が離せませんね。
続いてはこちらです!